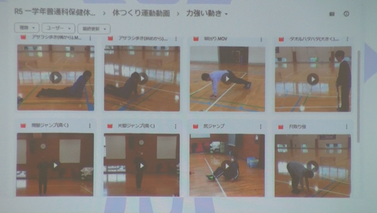第62回全国学校体育研究大会 山形大会 視察報告
北村 啓一
福島南高等学校 保健体育科
【基調報告】
大会主題
「生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現に向けて」
~三つの資質・能力をバランスよく育成する体育・保健体育学習の在り方~
主題設定の理由
・幼児児童生徒が身に付けることを目指す資質・能力を三つの柱で再整理し、内容等の改善を図る
・カリキュラム・マネジメントの充実、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた指導と評価の一体化
【解説】
「体育、保健体育を通した子供たちの確かな資質・能力の育成」
~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~
スポーツ庁教科調査官 塩見英樹氏
【シンポジウム】
「体育・保健体育における個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」
コーディネーター 東海大学教授 大越正大氏
【特別講演】
「豊かなスポーツライフの実現に向けて学校体育に期待するもの」
~「体育・スポーツの価値」と向き合う 新たな時代に向けて~
講師 東海大学教授 勝田隆氏
【公開授業(山形県立山形中央高等学校)】
「体つくり運動」~体ほぐしの運動、実生活に生かす運動の計画~
動きを高めるための運動の組み合わせをみつける
「体つくり運動」は生徒にとってあまり印象に残らない可能性がある領域といえる。そこで、「如何に印象深いものにするか」「実生活及び他の領域で如何に活用できる場面を増やすか」ということを目標に授業が展開されていた。授業内で使用された運動の参考映像や画像も自校の教職員に撮影協力を得た上で編集され、「体ほぐしの運動」や「実生活に生かす運動の計画」の説明時に、より生徒が親しみやすく、理解しやすいものとなるように工夫されていた。体を動かすことが好きな生徒、運動が得意な生徒からすれば各運動の難易度は易しいものであったが、学習内容の定着が図られれば、生涯を通じて心身ともに健康な生活を送ることができるヒントになると思えた。また、それぞれの運動は特別な技能を必要としないため、誰もが楽しみながら運動することができると感じた。
ICTの環境については体育館や教室に整備が進んでいるようで、様々な学習支援ツールを積極的に活用し、課題達成のために収集した資料や成果、学んだことや気付いた点などの記録が手元に残るように工夫されていた。